医療者と医療に関心がある人のためのカント倫理学入門
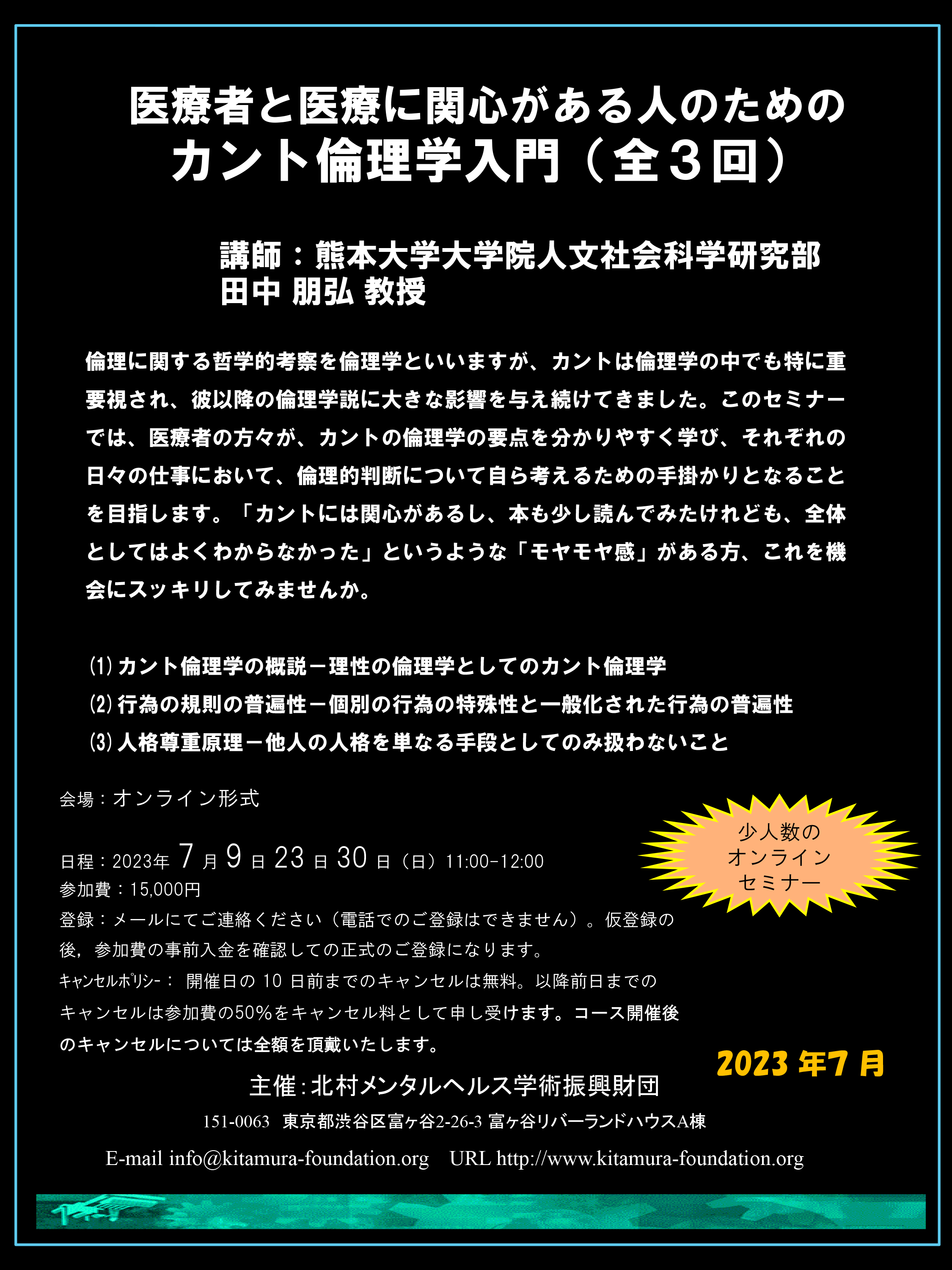
ご登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。
キャンセルポリシー:10 日前までのキャンセルは無料 以降前日までのキャンセルは参加費の50%を,当日のキャンセルは全額をキャンセル料として申し受けます。
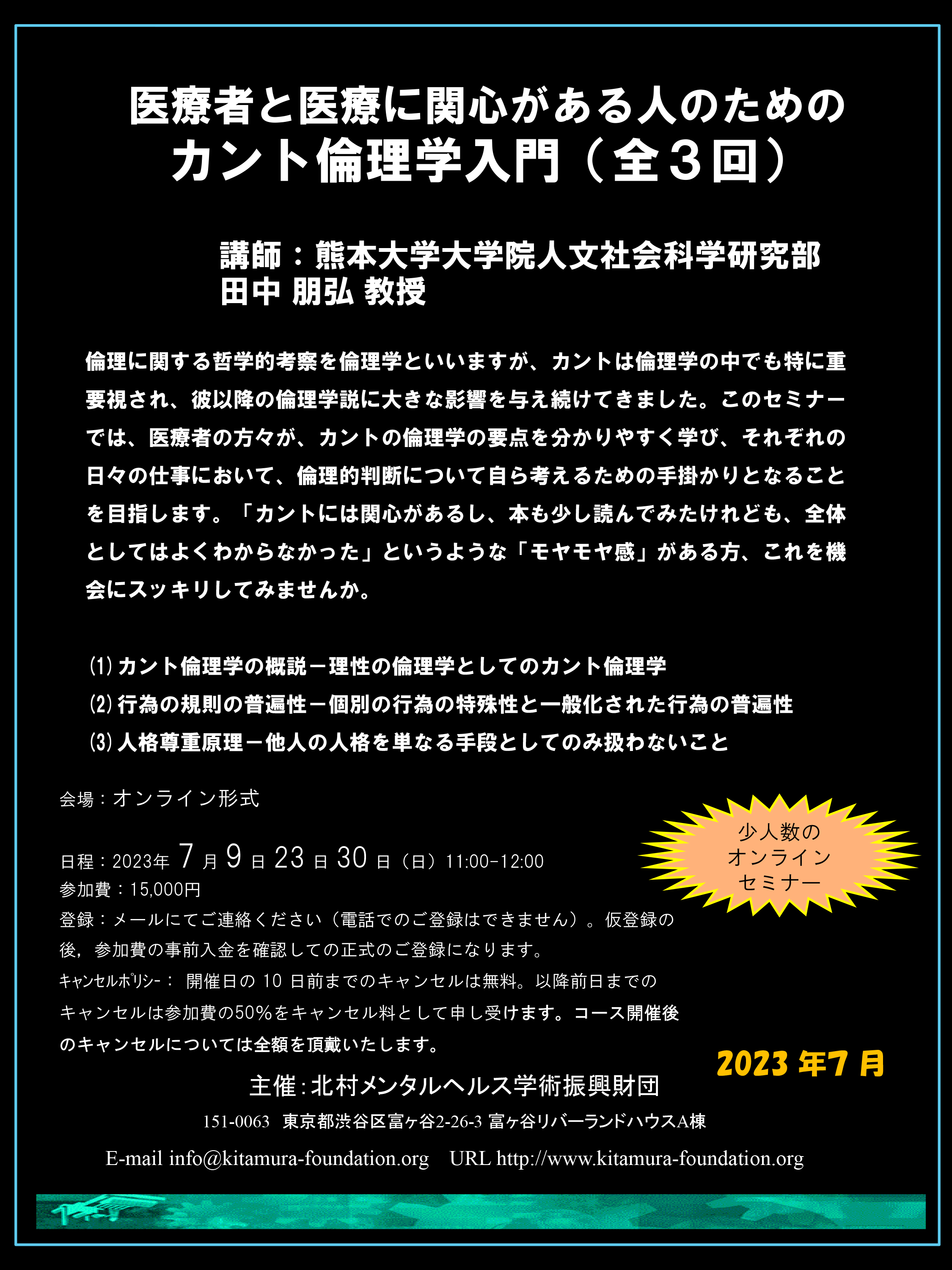
ご登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。
キャンセルポリシー:10 日前までのキャンセルは無料 以降前日までのキャンセルは参加費の50%を,当日のキャンセルは全額をキャンセル料として申し受けます。
| 日程 | 2020年 11月29日 日曜日 10:30-16:30 日程変更しました |
|---|---|
| 会場 | ウエブ会議方式によるネット・セミナー |
| 内容 | 周産期メンタルヘルスケアの重要課題のひとつであるボンディング障害について、その心理治療の実際を、古典的論文の紹介と架空事例の供覧から、分りやすく解説します。 |
| 参加費 | 4,000円 |
| 申込書 |
メールにてお申し込みください。 |
| プログラム |
1:古典を学ぶ:フレイバーグと赤ちゃん部屋のお化け担当:大橋優紀子 文献:Fraiburg, S., Adelson, E., & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the nursery: A psychoanalytic approach to the problems of impaired infant-mother relationships. Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 14(3), 387-421. 2:事例担当:北村俊則 お化けの発見とその退治を行なう。 3:古典を学ぶ:アンナ・フロイトと防衛機制担当:斉藤友見 文献:Freud, A. (1936). The ego and the mechanism of defence. New York: International Universities Press. Rev. ed., 1966. 4:事例担当:北村俊則 ボンディング障害における防衛の実際とそれへの対応の実際 5:古典を学ぶ:シュビングと患者への寄添い担当:松長麻美 文献:ゲルトルート・シュヴィング(著)小川信男、船渡川佐知子(訳) (1966) 「精神病者の魂への道」みすず書房. 6:事例担当:北村俊則 21世紀の周産期メンタルヘルスケアの実践における「寄り添う」技法の説明 |
ご登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。
キャンセルポリシー:10 日前までのキャンセルは無料 以降前日までのキャンセルは参加費の50%を,当日のキャンセルは全額をキャンセル料として申し受けます。
| 日程 | 2019年11月17日 日曜日 10:30-16:30 |
|---|---|
| 会場 | 社会福祉法人聖母会 聖母病院 5階講義室 |
| 内容 | 周産期メンタルヘルスケアの重要課題のひとつであるボンディング障害について、最近の研究の進展について、分りやすく解説します。 |
| 参加費 | 4,000円 |
| 募集人員 | 募集人員(50名)に達し次第締め切ります。 |
| 申込書 | |
| プログラム |
|
受講申し込み:北村メンタルヘルス学術振興財団ホームページから申し込み書(EXCEL FILE)をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メール添付にて当財団にお申し込みください。
ご登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。
キャンセルポリシー:10 日前までのキャンセルは無料 以降前日までのキャンセルは参加費の50%を,当日のキャンセルは全額をキャンセル料として申し受けます。
| 日程 | 2019年6月30日 日曜日 13:00-16:20 |
|---|---|
| 会場 | 社会福祉法人聖母会 聖母病院 5階講義室 |
| 内容 | 周産期メンタルヘルスケアの重要課題のひとつであるボンディング障害について事例を供覧し、その治療的かかわりの実際と、理論的背景の説明を行います。 |
| 参加費 | 2,500円 |
| 募集人員 | 募集人員(50名)に達し次第締め切ります。 |
| 申込書 | |
| プログラム |
|
受講申し込み:北村メンタルヘルス学術振興財団ホームページから申し込み書(EXCEL FILE)をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メール添付にて当財団にお申し込みください。
ご登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。
キャンセルポリシー:10 日前までのキャンセルは無料 以降前日までのキャンセルは参加費の50%を,当日のキャンセルは全額をキャンセル料として申し受けます。
| 日程 | 2018年11月11日 10:00-17:00 |
|---|---|
| 会場 | 社会福祉法人聖母会 聖母病院 5階講義室 (西武新宿線下落合,西武池袋線椎名町) |
| 内容 | 周産期精神医学においては従来、気分障害と不安障害が注目されてきました。しかし、母(そして父)の胎児・新生児に対するボンディングの障害が重要であることが、次第に認識されるようになってきています。この領域の国際誌を見ても、産後うつ病を主題とした論文数が減るのに呼応して、ボンディング障害を主題とする論文数が増加しています。本セミナーは、その第1回からボンディングとその障害について、概念、測定方法、疫学、経過、発症要因について検討してきました。今回はエビデンスとしてこれまでに何が明らかになっているのかについて発表を行います。あわせて、今後の課題について検討します。また、研究成果を理解する上で必要な基礎用語や概念についてミニレクチャーを行なうことで、理解を深めていただく予定です。 |
| 参加費 | 4,000円 |
| 募集人員 | 募集人員(50名)に達し次第締め切ります。 |
| 申込書 | |
| プログラム |
基本用語の理解
エビデンスと課題
|
受講申し込み:北村メンタルヘルス学術振興財団ホームページから申し込み書(EXCEL FILE)をダウンロードし、必要事項をご記入の上、メール添付にて当財団にお申し込みください。
ご登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。
キャンセルポリシー:10 日前までのキャンセルは無料 以降前日までのキャンセルは参加費の50%を,当日のキャンセルは全額をキャンセル料として申し受けます。
| 日程 | 2018年4月22日 10:00-17:00 |
|---|---|
| 会場 | 社会福祉法人聖母会 聖母病院 5階講義室 (西武新宿線下落合,西武池袋線椎名町) |
| 内容 | これまで3回にわたって周産期ボンディング障害をテーマとしてセミナーを開催してきました。 今回は3症例ほどを提示し、その経過、治療方針と実施、転帰について提示し、加えて治療方針の基礎にあるこれまでの研究所見についてミニ解説をつけます。 |
| 参加費 | 4,000円 |
| 募集人員 | 募集人員(50名)に達し次第締め切ります。 |
| 申込書 |
ご登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。
キャンセルポリシー:10 日前までのキャンセルは無料 以降前日までのキャンセルは参加費の50%を,当日のキャンセルは全額をキャンセル料として申し受けます。
第3回周産期メンタルヘルスセミナー周産期のボンディングとボンディング障害
御登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。 一般演題マターナルボンディングと母親の睡眠の質、うつ症状との関係―産後1ヶ月健診での横断的調査― はじめにマターナルボンディング(母親の子への情緒的な絆)は子の健全な発育のために重要である。多くの母親がマターナルボンディングを形成するのは産後 3 か月頃といわれるが、形成途中である産後早期のマターナルボンディングが虐待的育児の素因となること(北村, 高馬, 多田, 2014)や、産後 1~4 週時のマターナルボンディングが1 年後のマターナルボンディングへ影響すること (O'Higgins, Roberts, Glover, & Taylor, 2013) から産後早期のマターナルボンディングは重要である。産後 1 か月時のマターナルボンディングへ母親の睡眠の質、うつ症状、子どもの数が影響していることが明らかになった 方法1. 研究デザイン:相関関係的研究デザイン 結果
子どもの数はマターナルボンディングへ有意なパスを示し、マターナルボンディングはうつ症状へ有意なパスを示していた(図1)。 結論産後 1 か月時の子どもへの否定的な感情がうつ症状へ影響すると予測されることから、産後早期からボンディング障害へ着目した支援を行うことが産後うつ予防の意味でも重要と示唆された。 参考文献北村俊則, 高馬章江, 多田克彦. (2014, 11月) .新生児虐待の原因は産後の抑うつ状態ではなくボンディング障害である:岡山地区疫学調査から.第11回日本周産期メンタルヘルス研究会学術集会プログラム・抄録集 (p22), 埼玉県.
周産期女性のソーシャルサポートはボンディング障害と抑うつ状態に対して保護的な働きを持つ:前向きコホート研究を用いた検討結果 目的周産期女性が感じるソーシャルサポート(周囲からのサポート)の有無が、母から子へのボンディング(愛着)障害及び抑うつ状態に与える影響を、前向きコホート研究結果を用いて明確化する。 方法2004 年 8 月から 2015 年 11 月まで一般成人妊婦 1031 人を対象に、妊娠初期と産後 1 ヶ月に、ソーシャルサポート、ボンディング障害、抑うつ状態各々の自記式質問紙である、Japanese version of the Social Support Questionnaire (J-SSQ)、Mother-Infant Bonding Questionnaire (MIBQ)、Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)、への回答を依頼し、494名(32.4+4.5歳)より全回答を得た。J-SSQ、MIBQ、EPDS、の各下位尺度を変数として設定し、各変数の関係性についてパスモデルを作成し、共分散構造分析を用いて解析した。 結果妊娠中のサポート提供者の数の主観的な少なさは、(1)産後のボンディング障害を直接的に予測し(p < .01, r = -.17)、(2)妊娠中のボンディング障害の増強を経由して、産後のボンディング障害を間接的に予測した(p < .01, r = -.19)。更に、(3)産後の抑うつ状態を直接的に予測し(p < .01, r = -.10)、
図1 ボンディング障害・抑うつ状態・ 妊娠の計画性と妊婦のアタッチメントスタイルとの関連-パスモデルによる因果の検討- はじめに妊娠の計画性は、妊娠の受容に対する態度への影響をはじめ、妊娠中の生活行動、胎児への愛着形成、妊婦のQOL、育児期における夫婦関係、さらに、夫の対児感情にまで関連する因子である。 方法調査期間 H 28 年 7 月~H 29 年 1 月、埼玉県内の 4 つの病産院に通う妊娠経過に大きな異常のない妊娠26週以降の初産婦に研究協力依頼し、同意を得られた方に自己記入式質問紙調査を実施した。 結果376 部配布、334 部回収(回収率 88.8%)、分析対象 321 部(有効回答率 96.1%)、平均年齢 31.9(SD 4.9)歳、平均妊娠週数 32.8(SD 2.9)週、計画的妊娠(希望した妊娠) 262 名(81.6%)、予期せぬ妊娠 59 名(18.4%)であった。
図1 本研究のモデル 最終的なパスモデルの適合度は、χ2乗検定 = 2.66、自由度 = 4、CFI =.970、RMSEA = 0.072であった。妊婦のアタッチメントスタイルは、妊娠の計画性に有意に影響していたが、妊娠の計画性からアタッチメントスタイルへのパスは有意ではなかった。妊婦のアタッチメントスタイルが妊娠の計画性に影響を及ぼすという因果関係が確認された。 考察アタッチメントスタイルの測定と妊娠の計画性を同時に調査した場合、アタッチメントスタイルが妊娠の計画性に影響しているという時系列が成立することが示唆された。 参考文献Bartholomew, K. & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of four-case category model. Journal of Personality and Social psychology,61, 226-244 助産師を中心とする看護職に対する心理支援技法研修が「こころに配慮する能力」に与える影響について はじめに心理援助を行うにあたり、患者の状態を心理的なものであると認識する能力の獲得は不可欠である。 目的周産期メンタルヘルス技術習得のための研修を実施する際、研修参加者の「患者の状態を心理的なものであると認識する能力」を研修前後で測定し、研修がこうした能力を向上させうるかを調査した。 方法対象 46 人(助産師 25 人、保健師 18 人、看護師 2 人、看護学生 1 人)に対し、 2007 年に心理援助技法研修を 5 回行った。研修は(1)各自の自習(2)講義(3)ロールプレイによる技術の習得を主な柱とし、内容は産後うつ病予防介入プログラム (Zlotnick, et al., 2001) を使用。心理的理解力を Psychological Mindedness Scale (PMS: Conte, et al., 1990) で、パーソナリティは Temperament and Character Inventory (TCI: Cloninger,et al., 1994) で、それぞれ研修の前後で測定した。 結果研修前後で、PMS 得点は有意に上昇した。また TCI の下位尺度では損害回避 (Harm Avoidance; HA) が低下し、持続 (Persistence; P) および自己志向性 elf-Directedness; SD) が上昇した。 考察心理的理解力は心理支援技法に特化した研修により上昇する。スタッスの心理理援助能力向上に繋がるかもしれない。
図 共分散構造分析(PMS, SD, HD) 参考文献Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., & Wetzel, R. D. (1994). The Temperament and Character Inventory (TCI): A Guide to its Development and Use. Washington University, St Louis, Missouri: Centre for Psychobiology of Personality. |
| 日程 | 2017年4月29日 13:30-18:00 |
|---|---|
| 会場 | 北村メンタルヘルス学術振興財団会議室 (代々木上原、代々木公園、代々木八幡、駒場東大前) |
| 内容 |
|
| 参加費 | 5,000円 |
| 募集人員 | 12名まで 募集人員に達し次第締め切ります ※満席となりました |
御登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。
キャンセルポリシー:10 日前までのキャンセルは無料 以降前日までのキャンセルは参加費の50%を,当日のキャンセルは全額をキャンセル料として申し受けます。
| 日程 | 2016年8月7日 13:00-18:00 |
|---|---|
| 会場 | 北村メンタルヘルス学術振興財団会議室 (代々木上原、代々木公園、代々木八幡、駒場東大前) |
| 内容 | ・周産期ボンディング障害:概念と評価方法 山下洋(九州大学) ・診断的範疇としての産後のボンディング障害 松長麻美(国立精神・神経医療研究センター) ・産前のボンディングとボンディング障害 臼井由利子(東京大学) ・産後の心理的虐待に与えるボンディング障害の影響 大橋優紀子(文京学院大学) ・周産期ボンディング障害:分類と要因 中村由嘉子(名古屋大学) ・総合討論 |
| 参加費 | 8,000円 |
| 募集人員 | 12名まで 募集人員に達し次第締め切ります |
御登録:メールでお申し込みください。満席になり次第、締め切ります。
キャンセルポリシー:10 日前までのキャンセルは無料 以降前日までのキャンセルは参加費の50%を,当日のキャンセルは全額をキャンセル料として申し受けます。