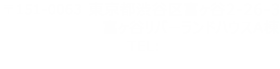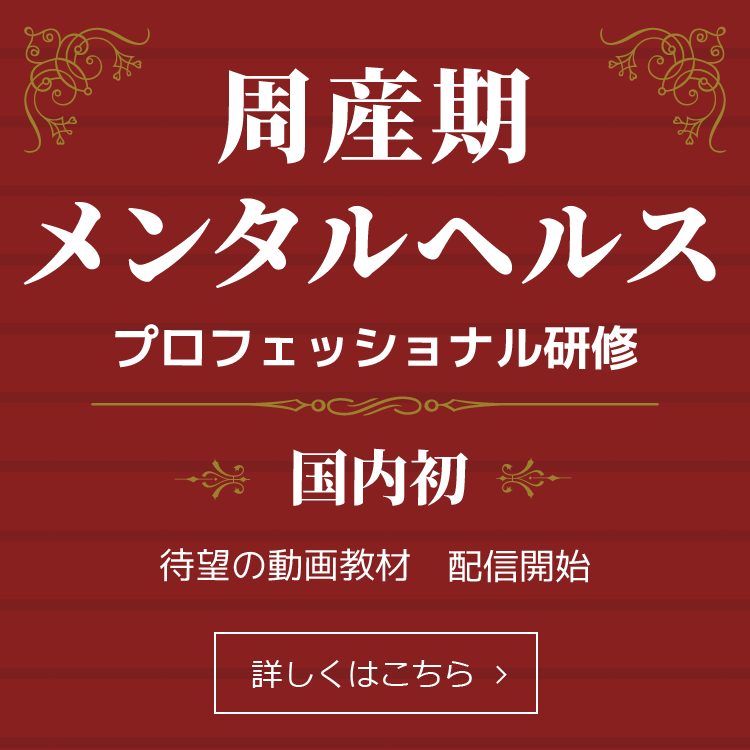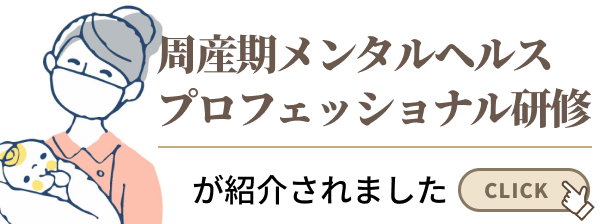受講者10名以上であれば、研修の出張をいたします。詳細はメールでお問い合わせください。
専門級をめざす周産期心理支援技法講座
臨床で働きながら研究をしよう:統計の裏わざとSPSSの使い方【2024年度】
医療・福祉・教育現場で働いている医師・看護師・助産師・保健師・ケースワーカー・心理士・保育士の皆さんが、御自分の疑問について研究デザインを組んで、データを収集し、パソコンに入力してから、統計法も使って解析し、結果を報告できるようになるための連続研修会です。研究デザイン・使用する尺度・統計法・レポートの書き方は表裏一体です。実例を基礎に研究と統計の基礎を、ミニレクチャーとSPSSの実習を通じて学びます。数学の専門家はだれも教えてくれなかった「裏技」を教授します。さらに査読対策や研究倫理についても理解を深めます。
| 入門編 | 2024年5月開講 |
|---|---|
| 中級編 | 2024年9月開講 |
| 上級編 | 2025年1月開講 |
北村メンタルヘルス学術振興財団での研修を受講して
大原聖子(名古屋大学大学院医学系研究科 精神医学分野 医師)
私は医学部卒業後、間もなく博士号取得を目指しましたが、妊娠・出産が重なり諦めました。その後、育児をしながら児童精神科臨床を続けていましたが、臨床上の疑問を臨床研究に具体化したいという思いは日に日に強くなりました。家族の応援もあり二児の母として博士号取得へ再挑戦する事となりましたが、卒後15年というブランクはとても大きく、また自分の力の無さに愕然としました。そこで意を決し北村メンタルヘルス研究所を訪れました。その時の事は、今でも鮮明に覚えています。
その後、名大で博士課程の大学院生として研究生活を送りながら、北村先生のもとで学びました。私は「臨床で働きながら研究をしよう:統計の裏技とSPSSの使い方」および「パーソナルリサーチテューターサービス」を受講しました。統計技法に留まらず、研究の発案から論文執筆における論旨の整合性に至るまで、研究遂行において押さえるべき事柄を網羅しており、学びの多い濃厚な時間を過ごす事ができました。
北村先生のもとで学んだ3年間、辛く苦しいだろう統計の勉強や論文執筆は、いつの間にか“学ぶ楽しさ”“学ぶ喜び”と変わり、私の研究生活は色鮮やかなものとなりました。最終的に、短縮修了として博士号を取得できただけでなく、更にPsychiatry and Clinical Neurosciencesのフォリア賞を受賞する事ができ、北村先生に心より深く感謝申し上げます。博士号取得はスタート地点であり、研究生活は一生である-という言葉を胸に、これからも臨床に寄与すべく研究を進めて行きたいと思っています。
「臨床で働きながら研究をしよう:統計の裏技とSPSSの使い方」を受講して
久保田 智香(名古屋大学 学生相談総合センター 特任助教 精神科医師)
私は大学院生として本講習を受講しました。当初は学会発表程度の経験しかなく、研究なんて右も左もわからない状態でしたが、全講習を終え、自分でも勉強を続けた結果、プロトコル作成、解析、論文のアクセプトまで遂行でき、大学院も無事卒業できました。
本講習を受講して良かった点は沢山あるのですが、できるだけシンプルに伝わるよう次の3つにまとめました。全てを伝えきることは到底できませんが、これで受講して良い結果を出す人が増えれば幸いです。
①測定することの大切さに気づく
私には、「統計=難しい」という先入観がありました。
しかし、本講習は、「何かを測定することの大切さ」を、まずは数式を使わずに言葉で説明するところから始まります。統計で使われる専門用語も一つ一つ噛み砕いて解説されるため、話についていけなくなってしまうことはありません。職種や年齢、経験の多寡を問わず楽しめる内容だと思います。SPSSの使い方についても、操作手順は省略することなくテキストに網羅されているため、家に帰ってからも復習することが容易いです。
講習会を学んだ後には「統計=楽しい、興味深い」に変わり、SPSSの操作にも抵抗感がなくなりました。
②研究が必ず一歩前進する
おそらく、この講習会を受けようか興味を持っている方々は、大学院生や教員など、何らかの形で研究に関っている場合が多いのではないかと思います。
本講習では、「臨床疑問をどのように研究計画書に書き示すか」「データは集まったがどう解析していくか」など、参加者それぞれがつまずいているポイントを聞いた上で、具体的な対策を一緒に考えてもらうことができました。皆さん、研究を行う上で沢山の悩みがあると思いますが、受講によって必ず一つは問題が解決することでしょう。私はその結果、良い論文が沢山書けるプロトコルを作成することに繋げられたと思います。
そして、本講習は、周産期メンタルヘルスに携わる人はもちろん、内科医、研究者など多くの立場の人が受講者として参加しています。これは副次的な利点といえるかもしれませんが、様々な領域で研究している人同士で情報交換でき、モチベーションアップにもつながりました。
③研究だけでなく、臨床・教育にも活かせる
例えば、私の場合は、論文を読む際、これまでアブストラクトの結果の部分だけを読んで済ませることも多かったのですが、受講後は、適切な方法で解析された上での結果なのか考えながら読むようになりました。そうすると論文をこれまでより面白く読めるようになり、国外の最新の文献にも手が伸びるようになりました。そうして得られた知識はより良い臨床活動につながっているように思います。
また、本講習では論文執筆の際に気をつける点(フォントや体裁を整え、論理的な文章を作成していくノウハウ)もいくつか教わったのですが、これは、論文執筆に限らず、ミーティングでの報告や学会発表などにも活かせています。そして、こうした充実した教育を受けることができたからこそ、後輩や他職種の人に同じように丁寧に説明する姿勢が得られたと感じています。